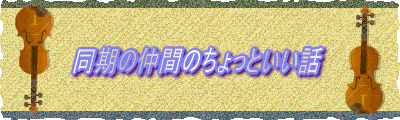
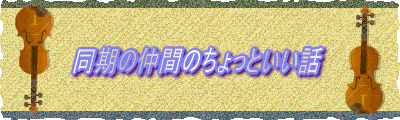
| 北原東代さんの最近発行されたばかりの著書 発行所:株式会社春秋社 発行日:二〇〇八年六月一八日第一刷発行 定価:一八〇〇円 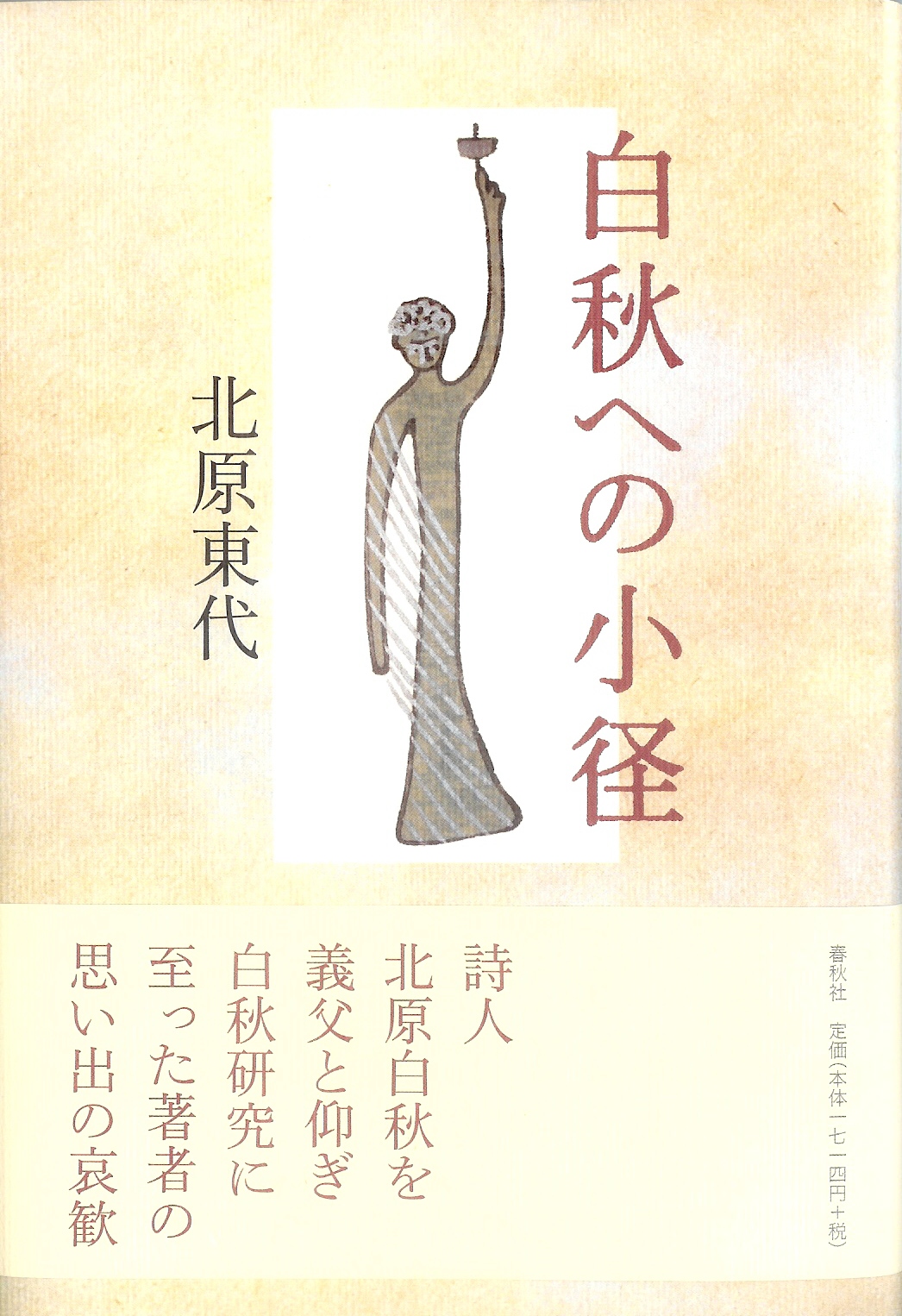 生れてきた甲斐 私が熊本県立玉名高校へ入学したのは、昭和三四(一九五九)年春である。 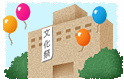 ちょうど、皇太子殿下(現、天皇)と美智子さまのご成婚で国中が沸いていたころだ。当時、テレビの普及はめざましかったが、母子家庭のわが家には無縁の事だった。 ところで、私が玉名高校に入学した時、担任の先生は私の顔の暗さに驚かれたそうだ。ずっと後になって、笑いながらそう言われたのだが、ふり返ってみると、中学時代の末期、私はすっかり厭世的になっていたので、自ずとそれが顔にも表れていたのだろう。 そのころの私は、全身が懐疑の そのような私がこの世と繋がっていたのは、苦労して育ててくれた母を悲しませたくない、というただ一つの理由でしかなかった。 ところが、入学した玉高で、心の琴線に触れる何人かの先生と何人かの友にめぐり会った。先ず、組分けに従って入った教室の私の隣席には、家が浄土真宗の寺で、ほのぼのと温かく明るい友がいた。担任の数学の先生は、「ヤマアラシ」というニックネームの茫洋と豊かで包容力のある方だった。   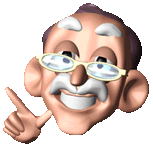  国語担当の、頭髪が天然パーマで、「万葉時代のあなたたちくらいの女性は、もうおしめを洗っていたんですよ」といったユーモアに満ちた先生や、ビルマ戦線の生き残りで東北 玉高の広々とした環境も良かった。とりわけ、あの樹木に囲まれた木造平屋の図書館は、私の安らぎの場であった。そこで借り出した多くの本によって、私は西欧文学に開眼した。 かくして、玉高での新たな日々の内に、私は生きる意欲を次第に回復していった。 クラブ活動では、一年の時は生物クラブに入り、夏休みに阿蘇と菊池の水源で二泊三日のキャンプを体験した――阿蘇の大草原で感激した私が逆立ちしている写真が残っている。 二年では、友人から誘われて演劇同好会を作り、講堂で劇を「上演」した。私はプロデューサーをつとめ、端役をも演じた。また、その友人と夏休みのある夜、玉高のプールへ泳ぎに行った。女二人、森閑としたプールで嬉々として泳ぎ回ったが、最後に私は、飛びこみ台からほぼ垂直に飛びこみ、プールの底で頭を打ち、痛かった。 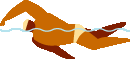 三年になって、受験勉強のため、自由に本が読めなくなったのは苦痛であった。だから周りの友人たちが薬学部や教育学部を志望する中で、最も本が読めて、私自身の内面の問い――人生とは何か、人生をいかに生きるか――に、じっくりと取り組めそうな文学部を選んだのである。 無事に大学に進み、図らずも禅哲学者、久松真一先生に出会った。私は、先生の清澄な光の漂うお顔を拝した瞬間、真に悟った方、と直感した。そして、「生れてきた甲斐があった」とよろこびに貫かれたのであった。 久松先生との出会いは、先生の説かれる「真実の自己」に目覚める道の始まりでしかなく、依然としてその途上にいる私ではあるが。 今、私は、玉名高校での師、友人、本との出合いによって、生きる意欲を回復し、さらに高めることができたことを (初出―「育友会だより」一〇四号、熊本県立玉名高校育友会、平成一一年一二月) ふるさとの山、 ―抜粋― 私のふるさとは、母の里の熊本県玉名市である。市になる前は玉名町、戦前は玉名郡 ・・・・・・・・・・・ 玉名町小学校入学はとても嬉しかった。  入学式の前晩は、胸がわくわくしてすぐには寝つかれなかったのを覚えている。しかし、期待した学校生活だったが、いざ始まると、村育ちの私は、幼稚園を経てきた町の子に気後れを覚え、友達もなかなかできなかった。 入学式の前晩は、胸がわくわくしてすぐには寝つかれなかったのを覚えている。しかし、期待した学校生活だったが、いざ始まると、村育ちの私は、幼稚園を経てきた町の子に気後れを覚え、友達もなかなかできなかった。小学校へ通う道から、畑のずっと向こうに小岱山が眺められた。富士山に似た形の良いその山は、左右に両腕を拡げたような裾野を有し堂々と 私はなぜか、ひとりで登下校することが多かった。それで、往きは、右手に小岱山を仰ぎ見ながら、「どうか今日は悪いことが起こりませんように」と、祈りながら歩くのだった。 だが、学校では嬉しいこともあったが、つらい、悲しいことが 私が六年間通った玉名町小学校の校歌は 小岱山の青あらし 流れはたえぬ菊池川 と、始まる。在学中、「校歌斉唱」の号令のもとにこの校歌を、意味などあまり考えず、どのくらい歌ったことだろう。  「小岱山」ということばの響きだけでも胸が熱くなるのは、この校歌のせいもあるかもしれない。石川啄木の、 ふるさとの山に向かいて 言うことなし ふるさとの山はありがたきかな (『一握の砂』) の歌を知ったのは、小学六年生の時だったが、私にとってのふるさとの山は、まさしく小岱山にほかならない。 ・・・・・・・・・・・ ともあれ、小岱山は懐かしい。今、私は、あの山は私を育ててくれた「親」のひとりであったような気さえしている。 (初出―「 外交官を夢みたころ 私の通った熊本県玉名市立玉名中学校は町と農村の境目に位置し、校舎の窓からはちまちました町中の家並と広々とした田んぼとが両方見渡せるところにあった。この中学に入学して、先ず私は一種の解放感を味わった。 というのは、小学五、六年の時の担任であった女のM先生は、根底に濃い愛情があってのことだが、男まさりの厳しい先生で、のんびり育った私など、よく「仕事が遅い」と叱りとばされたからである。実母がおとなしく優しい性質であっただけに、私はM先生を尊敬しながらも恐れ、時には圧迫されるような感じも抱いていた。 中学では科目ごとにいろいろな先生が入れ替わり、担任の図工の先生も淡々とした方で、もはやM先生の厳しく光る視線もなく、私は何となくほっとした気分であった。 こうして、すべてが目新しく感じられる授業の中で、最もひきこまれたのがI先生担当の英語の時間であった。I先生は大学を卒業してまだ二年目という若い男の先生で、少しニキビが残っているような丸顔に眼鏡をかけておられ、笑うと目が糸のように細くなり、力をこめて話をされる時はぐっと見開いた瞳が虎の両眼を思わせた。 先生の授業には「熱情」という二字がぴったりだったが、決して一本調子ではなく、ユーモアをたっぷり挟まれ、時にはピリッと胡椒をきかせられたりした。 「不規則動詞の変化はトイレで覚えるといいよ。show-ahowed-shown,put-put-putというふうに」と、リズミカルに発音されたことなど、思い出すごとに何度笑ったことだろう。教科書に出てくる英文を文章ごと覚える方法も教えて下さったが、これは実行して大いに役立った。 当時、私と高校生の姉は一つの部屋に机と並べていたので、姉が私の音読をうるさがることもあり、私は庭先の大きな柿の木によじ登っては、木の上で英文を声に出して暗誦したものである。 そして、有明海の対岸に聳えた紫にけむる雲仙岳を眺めながら、将来は東京の外語大学に進み、外交官になって広い世界を駆け巡りたい、と夢みるに至った。 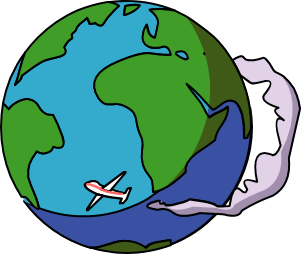 そこで外国切手の収集に凝ったり、厚顔にも当時の首相、岸信介氏に手紙を出したり(代理の安部洋子さんから返事がきた)、「郵便友の会新聞」に名前の出ていた米国の女生徒にI先生の添削を受けた英文の手紙を出したりした(これはなぜか返事がこなかった)。 結局、外交官にはなれなかったが、中学一年のころ外国への眼を開かせて下さったI先生に私は心から感謝している。といっても、年頭に賀状をさし上げるだけであるが。I先生からは今年も力のこもった独特の元気印の書体で、ご返事を頂いた。 (初出―広報「ふたば」、横浜国大附属中学校、昭和六二年七月一五日) 私は熊本県の玉名高校一年生の終りごろ、岩波文庫の西田幾多郎著『善の研究』を町の小さな本屋で買った。そして、重要と思われる箇所には赤い線を、意味不明の箇所には青い線を引きながら、懸命に読んだ。京都大学文学部への志望はここに芽生えた。 ・・・・・・・・ (初出―「心茶」三九号、心茶会、平成五年五月一日) 桜の陰影 ・・・・・・・・・・ 四年前の桜の季節に、少女時代からの親友、N子と永別して以来、桜は私に深い陰影を帯びて映るようになった。 N子とは、三十数年昔の春、郷里熊本の高校に入学して間もなく、「生物クラブ」で知り合った。N子は、涼しい瞳と栗色がかった髪の、色白の頬をよくぽっとバラ色に染める純真で快活な少女だった。三年生で同じクラスになり、親友となって以来、熊本と京都と遠く離れて住むようになっても、各々に結婚して母親となっても、三〇代、四〇代になっても、仲の良さには何ら変わりはなかった。 ・・・・・・・・・ (初出―「禅文化」一六四号、禅文化研究所、平成九年四月二五日) <熊本日日新聞に連載された記事> 平成11年7月5日〜9月27日、熊本日日新聞に連載された記事(13回分) 1、実父の眠る花岡山 2、めぐんでもらった話 3、白秋の作った校歌第一作 4、生粋の母国語 5、麦わら帽子 6、耳鳴り 7、敬愛する先輩女性 8、白秋の従弟 9、駅のこころ 10、クーラーなしの夏 11、母の乳 12、手紙について 13、真実の白秋 |
|